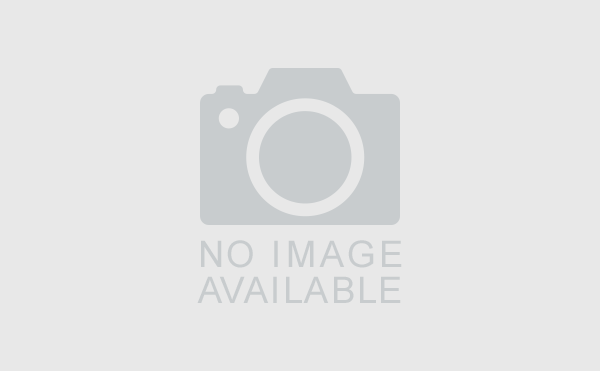ゆるいつながり 協調性でなく、共感性でつながる時代
著者:本田直之
発行所:朝日新聞出版
印象に残ったこと:
人脈とは、お互い情報を交換したり、刺激し合ったりして、一緒に成長していけるようなマインドの高い仲間のこと。そうした仲間を持つためには、「相手に対してなにができるのか常に考えていくこと。つまり(コントリビューション)(貢献)が不可欠である。 貢献するには、相手に提供できる「価値」を持っていなければならず、そのためには自分を常にアップデータしなければならない。:『レバレッジ人脈術』
ゆるいつながり:ゆるい、けれども深いつながり(一緒に成長していけるマインドの高い仲間たちの結びつき)
「人脈術」から「つながり方」へ
「人とのつながり方が、ゆるくなっている」
①人間関係が希薄なうようで、濃密。
②人と知り合うためのハードルが低い。
③知り合える人の幅が広く、多様。
④出る杭は伸ばされる。
ネットが生んだ「ゆるいつながり」(インターネットの登場により生まれた)
共感のコミュニティ
第1期「ゆるいつながり」:パソコン通信からメーリングリストまで
第2期「ゆるいつながり」:「ミクシィ」から「フェースブック」(人間関係の強制力、双方向、本名が基本)
第3期「ゆるいつながり」:「インスタグラム」(アカウント名、匿名可、フォロー-フォロワーの関係、不特定多数への発信)、「クラウンファウンディング」
SNSがつくる「ヨコ社会」
「昭和的強制のつながり」:「タテ社会」
①人間関係が濃密なのうで、希薄。
②人と知り合うたmのハードルが高い。
③知り合える人の幅が狭く、画一。
④出る杭は打たれる。
いやだけども、追随するしかない。
名刺交換
オフラインになる権利(2017年1月1日制定「フランスの労働者、勤務時間以外の仕事のメールを見なくても良いという権利」)
自分を高めないと、つながりはできない。必要なのは、強調性より、共感性
周囲の人間は、自分を映す鏡
つながりの基本は、「想像力」
「つながり」の5つの型
1.ハブ型:ネットワークの中心として人と人とをつなぐ
2.能力提供参加型:自分の(専門的・強みになる)能力をコミュニティに提供
3.フェースブック型(異業種交流会での名刺交換、「申請」と「承認」の手続きが必要)
4.共感型:単なる応援にとどまらず、行動的なサポートをともなう
5.プロジェクトチーム型:新しいエベントをやろうというときなどに、特別に集まって、仲間として一緒に行動する
ゆるいつながりに必要なこと
・相手への想像力
・共感を呼びセンス・オリジナリティ
・価値の提供・貢献
・多様性
・ヨコの人間関係
・共通言語・体験
・テクノロジーの知識
ゆるさこそ多様性の源
AI試合。人生100年時代を生き抜く、つながりの法則
「仕事と遊びの垣根をなくす」が、100歳時代を生き抜く力に
「オリジナリティ」を活かせる、から、ないと苦しい時代へ
時代についていくために、労力を惜しまない
「ゆるいつながり」こそが、AI時代を生き抜ける
所感:「昭和的強制のつながり」が悪いというわけではなく、その特性を理解し、共存していくことが必要。
時代に取り残されないように、時代の変化を把握し、対応していくことが必要と感じる。